69号 OPINION 特集【国立大学のこれから】
「知のインフラ」としての国立大学が真に個性を発揮するために必要なこと
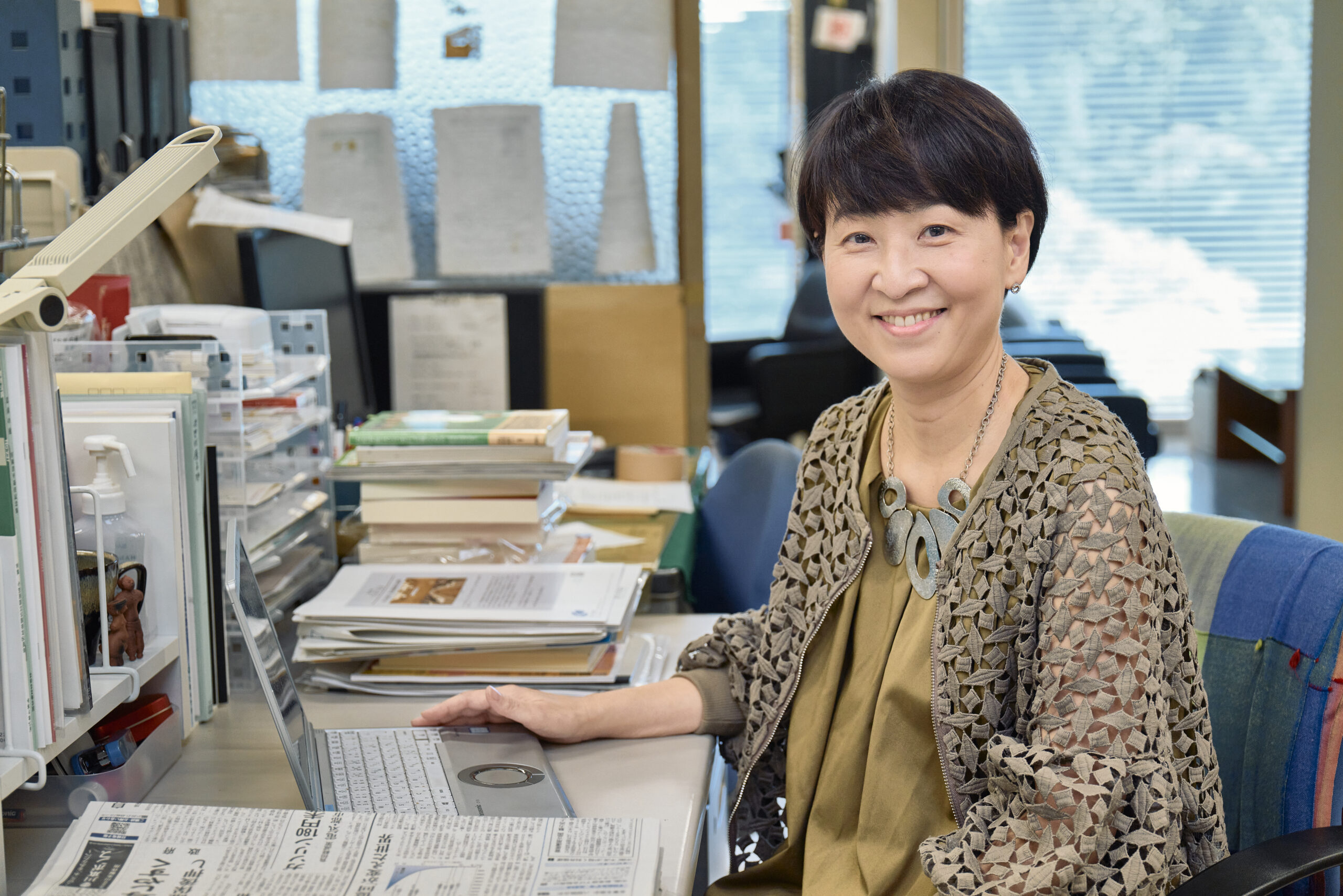
毎日新聞論説委員
元村 有希子
少子高齢化の流れはもはや止められない日本において、
国立大学はどのような姿を目指すのか?
資金、人材、時間が痩せ細っていく中で、学びの機会を担保し、
多様な研究の芽を育んでいくために、元村有希子氏は「大学の個性」に注目する。
そもそも個性とは何なのか。個性を発揮するために関係者はどうあるべきなのか。
約20 年にわたり、科学記者として多くの取材を重ねてきた元村氏が国立大学に望むこと、
その言葉に耳を傾けてみたい。
「選択と集中」が生んだものとは
日本の研究・教育全体をとりまく現状は「ズバリ、悲劇的な状況」と元村氏。それは「20年前には世界4位だった注目論文数が2023年には13位にまで後退した」といったデータに現れるだけでなく、「実際に大学で話を聞いていても、やはり研究基盤が脆くなっている」と感じるそうだ。
そう感じるのは、「金」「人」「時間」の3つの要素がどれも良くなっていないからだ。研究費は今や成果と紐づいた資金がメイン。運営費交付金が削られ、自由な発想に基づく研究がしづらくなっている。人については、基盤的経費の削減により十分な人数を確保できない。時間について言えば、秘書や技術員が削減される中で、彼らが担当していた仕事を研究者自身がしなければならないこと、大学が教育機能を強く求められる中でそちらに時間を割かれていること、さらに最近は、大学と社会との接点づくりが求められ、各種交流に時間を取られていることも課題となっている。
「これだけ金、人、時間が痩せ細っていけば、研究の自由度や自律性がしぼんでいくことは容易に想像できます」
こうした状況が問題なのは、「楽しいからやってみる」「結果が出るかはわからないけどやってみる」という、好奇心が駆動するような研究ができない、言わば「遊び」がなくなっているからだ。
「ノーベル賞を受賞した大隅良典先生のオートファジー研究は、光学顕微鏡でイースト菌を観察していて不思議な現象を見出し『面白いから』と始めたものでした。例えて言えば、昔は広い牧場に放牧されていた馬が、今は眼の前にニンジンをぶら下げられて必死で走っているよう。これでは研究者も頑張れないと思います」
国立大学の場合、こうなったきっかけはやはり2004年の国立大学法人化、正確には、それに伴う予算措置にあると元村氏は見ている。前提にあるのは小泉政権の「選択と集中」、すなわち費用対効果を重視し「勝てる」ところに金をかける思想だ。
「研究についても、『頑張った人に報いる』と言えば聞こえはよいのですが、結局『稼いだ人に報いる』ことになってしまっている。また政府は『基礎研究が大事だ』と言うものの、その基礎研究の中でも優遇される分野は偏っています。基礎研究にも『選択と集中』が及んでいて、『幅広い基礎研究』がないがしろにされているのではないでしょうか」
近年のノーベル賞受賞者を見ても、昨今の危機的状況を感じずにいられないという。
「私は2001年に科学記者になりましたが、その年に野依良治先生がノーベル賞を受賞されるなど、2000年以降の日本の学術界の勢いには素晴らしいものがありました。その後も日本人受賞者は出ていますが、ノーベル賞が映すのは15年かそれ以上前の姿。最近の日本人受賞者はアメリカの研究所の方だったり民間企業の方だったりで、21世紀における日本の学術界の成果は、受賞までのタイムラグが短かったiPS細胞だけと言っても過言ではありません。ですから、10年後は日本人の受賞者がいないか海外で業績を収めた日本人が受賞するなど、顔ぶれは今と全く違うものになっているでしょう」
長年の取材経験に加え、自らも国立大学の教壇に立つ元村氏。現在は、母校でもある九州大学の経営協議会委員も務めている。取材を通じ、旧帝大から地方大学まで多様な大学を見てきた立場から、たくさんのエールを頂いた。
「個性を伸ばす」はずの法人化なのに
国立大学法人化の際には、世界のトップを目指して競争するだけでなく、各大学の個性を伸ばすことも期待されていたはずだ。そうなっていない理由の一つとして、元村氏は学長のリーダーシップを巡る問題を指摘する。
「学長は基本的に何かの専門家で学内から選ばれる人であり、経営のプロではありません。だからこそ、大学の立ち位置を見極めて戦略を立てるには、様々な人の意見を聞き、広い視野を保つ民主的な運営が重要なわけです。ところが、政府が『学長のリーダーシップ』を強調しているため、中には『自分が決めなければ』と思ってしまう方もいる。一方で理事会は『最後は学長が決めるんだから』とか『こんな提案をしても学長がうんと言わない』と忖度を働かせてしまい、結果として誤った方向に進んでしまっているケースもあるように感じます」
もう一つは、大学同士、教員同士の横並び意識だ。
「先ほど『教育に時間を取られ過ぎている』と言いましたが、86の国立大学が全て同じように教育をする必要はないはずです。教育に特化する大学も研究に特化する大学もあってよく、大学院改革などもそのためのものでした。せっかく法人化したのだから、大学ごとにもっと違いがあってもよいし、先生方ももっと流動化して、よりご自分が輝く場所を見つければよいのです。また、財政的に厳しい大学は『お金がないので好きなことをやらせてもらいます』と開き直ってもよいのに、どうしても他と同じものを揃えようとしているように感じます。地方にある大学は地域に溶け込んでいることが大事なのに、東京や文部科学省の顔色ばかり窺っていては、個性の出しようがありません」
もっとも、背景には、国が「法人化したから自由にやれ」と突き放す一方で、文部科学省は一律にコントロールしようとしているように感じられる、という矛盾した状況もある。
「大学としてはどうしていけばよいのか、とても難しいところですよね」
起爆剤としての総合振興パッケージ
元村氏は、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」には、大学が多様化していく起爆剤としての役割を期待しているという。
「『国際卓越研究大学』として、いわゆる10兆円ファンドの支援先に選ばれるのは難しくても、『地域中核』にならチャレンジできる、と頑張っている大学の話も聞きます。実際には施策の対象に選ばれる大学は限られていますが、応募のために計画をつくることにも意義があると思うのです」
実はこうした「特色」による競争は本来、2004年の国立大学法人化のときに始まっていたはずだったのだが、「『国立大学』として歩調を合わせ、様子見を重ね、延命してきたのが今の状態」と元村氏。法人化から約20年経った今、いよいよ本当の競争時代が始まるということなのかもしれない。
「その競争というのも、全員が同じトラックで競うという発想ではなく、『別のフィールドで一番になる』ということを打ち出していかなければなりません。そうでなければ、今後はいよいよ学生に選ばれなくなるでしょう。受験生が減る、定員割れする、収入も減って先生が減る、特色ある取組ができなくなるという、悪循環になりかねません」
知のインフラとしてユニバーサルから機能分担へ
国立大学は、地方の大学であっても総合大学が多いが、個性や特色を出すためには、ある程度特定の学部にリソースを集中してもよいのではと元村氏は説く。
「特に研究においてはもっと特色があってよいと思います。例えば山梨大学が醸造に特化した研究を行っていたり、富山大学が富山湾とその生態系に関する研究に力を入れていたりしますが、そうした地域色が強まるほど面白いのではないでしょうか」
教育についても、どこにいても同じような教育が受けられるというこれまでの原則は成り立たないのが現実だ。
「ユニバーサルな教育サービスが成立していたのは、国が100%面倒を見ていた時代の国立大学だからこそ。今は当時とは違います。もちろん、高等教育を受けるためのオプションが全くなくなれば問題ですが、狭い日本でそういうことはまず考えづらい。もし自宅のすぐ近くに学びたいことが学べる大学がなくても、自宅から通う前提で大学を選ばなくてもよいような財政支援、例えば学費の免除や奨学金などが充実していれば、地元を離れて学ぶこともできるわけです」
さらに少子化社会において、国立大学が従来のように総合大学として現在の数を維持しようとすれば、一つ一つの規模は小さくせざるを得ない。しかし、それで学生へのサービスの質が低下しては本末転倒。大切なのは「社会のために何ができるか」だ。
「総合大学として維持したいがために規模が小さくなり、学生に『この大学はつまらない』と思われるというのはおかしな話。それよりは、この大学は医学系、この大学は工学系、この大学は人文社会系というように、それぞれ得意分野を打ち出して機能分担をする方がよいと私は思います。大学の中にいる先生方が、今の形を維持したいと思う気持ちはわかります。ただ、約30年前に銀行の再編統合があった頃、当時は銀行が潰れる、合併するというようなことを誰も想像していませんでした。社会のニーズに合わないのであれば規模を縮小したり合併したりするということはごく普通の民間企業の発想。大学も例外ではありません。大切なのは、『自分たちは社会にどう貢献するのか』ということを最上位に置き、そのために最適な形や手法を考えることではないでしょうか。なぜなら、大学は『知のインフラ』だから。公共のインフラにとって、『自分たちの看板を守る』ことの優先順位は二の次。やはり、社会への貢献を最優先して考えるべきだと思います」
機能分担の原点はアイデンティティ 限られたリソースは共有して補完
とはいえ、大学ごとに機能分担するとなると、今まで総合大学であったからこそ保たれていた人材の多様性が失われたり、大学としての能力が限定されたりする懸念はないだろうか。例えば、実験設備の有無などにより得意分野を分担しやすそうな理工系と比較して、「やろうと思えばどこでもできる」人文社会系の学問が再び軽視される可能性も気になる。
「私自身は、地域色をより強く反映するのはむしろ人文社会系の方だと思っています。社会学、文化人類学、考古学、博物館学のような、土地や風土に関することをより深く調べていく学問は、特色を出すという意味ではむしろ守られるべきだと考えています」
また、地方の大学が「地域色」をアイデンティティとしていくためには、「学部の壁を低くする」ことも重要で、そのことが「非効率」と言われがちな学問の存在意義を高めることにもなると元村氏は考えている。
「例えば、環境というテーマはとても幅広い分野の学問を含んでいますが、ある地域の環境問題について、そこの大学に行けばどの先生に聞いてもちゃんと応じてもらえる、という状態は、私たちのように取材をする者にとってもありがたいものです。一例として、水俣病という公害を経験した熊本では、医学、工学、文学など多様な分野の先生方が、「水俣学」という総合的な領域で現代社会に通じる研究に取り組んでおり、それがまさに大学のアイデンティティともなっています。そういう確かな存在感があれば、『この学問は非効率だからなくす』というようなことにもならないはずなのです」
つまり、元村氏の言う機能分担とは、中央から機械的に割り振るようなものではなく、「各大学のアイデンティティに沿ってなされるもの」だということ。そのためにもまずは、自分の大学のアイデンティティとは何か?という問いに答えなければならない。私立大学と違って「建学の精神」がない国立大学には難しいことだが、取り組んでいくべき課題と言えそうだ。
とはいえ、一つの大学の中に全ての分野が「学部」として存在するべきだとは元村氏は考えていない。
「社会課題の解決のためには文理融合が不可欠であり、そのために総合大学は理想的ではありますが、今や現実的に全ての機能を日本全国津々浦々で提供することはできません。教育についてはオンライン化して補い合い、研究については越境して行うことも現実解の一つではないかと思います」
究極の問いとして「総合大学として維持しつつ統合して数を減らす」のか、「数を残しつつ機能分担する」のか-この二択であれば元村氏はやはり後者を支持するそうだ。
「理由は、選択肢が多い方が豊かだからです。再編して数を減らし、一つ一つがユニバーシティの体裁を整え、似たような大学になるよりは、道の駅のように各地方に必ずあって、『ここの大学はこれが面白い』という状態の方が、受験生としても社会から見ても心強い。そして、その役割を担うのが国立大学であるべき理由は、やはり国立大学は『研究の場』だと思うからです。『当たりくじ』とは限らない分野にもきちんと投資をすることは、私立大学にはできないことであり、その中から将来、国が稼ぐネタが生まれ、集まった学生の中から次の研究を担う人材が出てくるかもしれない。そういう期待を担保する場として、国立大学はなくてはならないものだと思うのです」
経営でも学生でも、ジェンダー問題への対応は急務
もう一つ、元村氏がぜひ伝えたいのがジェンダーアンバランスの問題だ。
「現在、国立大学の学長は圧倒的に男性が多く、経営ボードも9割が男性です。どんな世の中にしたいのか、地域にどう貢献したいのかというデザインを描くときに、現状ではあまりにもアンバランス。国立大学が取り組むべき課題はいろいろありますが、まずはこのアンバランスを解消するのが最低ラインだと私は思います」
とはいえ、大学の経営ボードを目指せる女性人材は非常に少ないのも現実。どうやって女性を増やすのか?
「一つは外から連れてくることですよね。海外のアカデミア、あるいは日本の財界からでもよいと思います。そこにも人材がいないというならば、抜擢の仕組みを変えてもよい。例えば今から女性准教授を倍増したとして、彼らが学長として適齢期になるには15年くらいかかります。それなら適齢期を下げてしまうのも一つの方法では。実際、海外の大学では40代で学長になる例もあります。まずは女性の理事を増やしてほしい。この場合、1人ではなく、複数であるべきです。『女性の方がなりたがらない』というのはよく聞く課題の一つですが、発想や文化を共有する男性ばかりの中で「紅一点」は辛いもので、やりたくない気持ちもわかります。本当は全体の3割を超えてほしいところですが、まずは2人、任命してもらいたいですね」
また、女子学生についてはどうか。「リケジョは増えて当たり前なのに、増えない何かがあるのでしょう。高校の進路指導の段階で文系に誘導されてしまったり、家庭で『そんなに頑張らなくてもいいんだよ、女の子は』とつい言ってしまう大人は結構いたりします。人生にチャレンジする前から、複合的なハードルを設けられているのは、すごくもったいない」
「国立大学というからには率先垂範してジェンダーアンバランスの解消に取り組むべきで、それなくして『多様性』と言っても信用してもらえないでしょう」
知的資源の源泉を育成する場として研鑽を重ね、使命を全うしてほしい
「国立大学は社会の公器」と元村氏は言う。そして、そんな国立大学に対してだからこそ「いかに理想と現実の乖離が大きくても、諦めや妥協は禁物です」と訴える。
「国立大学の構成員の皆さんの間には、『国立』であり『法人』であるという狭間で戸惑いのようなものがあるのではないかと思います。しかし、都合によって両者を使い分け、現状に安住するようなことはしないでいただきたい。日本は資源小国なのだから、知的資源で生きていく、という方向性に異論はないでしょう。であればこそ、知的資源の源泉となる人材を揺るぎない信念を持って育成する場が必要で、それが国立大学なのではないでしょうか。国立大学の現状が全て国のお金が減らされた結果だとは言いませんが、国立大学たる活動ができるためにはやはり、金と人で支える必要があります。国からのお金が足りなければ『もっと寄こせ』と言えばいいのです。その代わりに自己研鑽も求められます。改革を恐れず、それぞれの大学が社会とのコミュニケーションを通して築き上げる使命を全うしていただきたいと思います」

元村 有希子(もとむら ゆきこ)
1966年生まれ。福岡県出身。九州大学教育学部卒業。1989年毎日新聞社入社。西部本社、東京本社科学環境部、デジタル報道センター、科学環境部長などを経て、2019年より論説委員。「理系白書」の報道で第1回科学ジャーナリスト大賞を受賞。現在は東北大学、富山大学などで教壇に立つ。毎日新聞にてコラム『水説』、サンデー毎日にて『淑女の養生訓』を連載。著書に『科学のトリセツ』(毎日新聞出版)、『カガク力を強くする!』(岩波ジュニア新書)など。
